公益財団法人同盟育成会は10月4日、2025年度の第1回奨学生研修会をオンライン形式で開催しました。奨学生や、財団の理事や奨学生選考委員など70人以上が視聴しました。従来、オンライン研修会は9月の平日に開催していましたが、奨学生のアンケート結果や大学事務局の意見を踏まえ、10月の土曜日に変更しました。この結果、奨学生の参加者は前年度に比べ15人程度増えています。
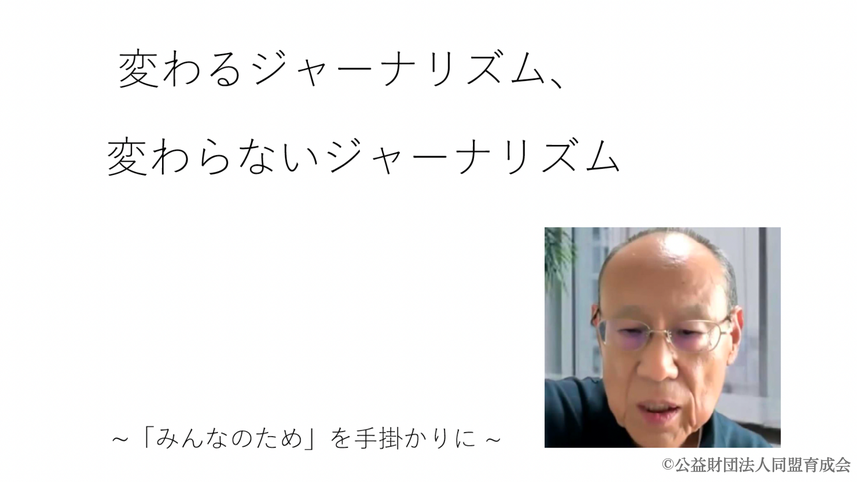
研修会では、福山正喜理事長のあいさつに続いて、橋場義之元上智大学教授が「変わるジャーナリズム、変わらないジャーナリズム~『みんなのため』を手掛かりに」と題して講演しました。この中で、マス・コミュニケーションのあり様は「社会のあり様の変化」と「コミュニケーション技術の発展」に伴い、変ぼうを遂げてきていると分析。社会の多様化、多極化によって「多数派(=ほぼみんな)が消滅している」と解説しました。一方で、ニュースが求めている3つの要素「生きる(生き延びる、より良く生きる)ため」「位置の確認(どこから来て、どこにいて、どこへ行こうとしているのか)」「知る喜び(おもしろがる)」は変わらないと指摘し、「事実に基づき」「公正で」「誠実」というジャーナリズムの規律を守ることが重要だと強調しました。
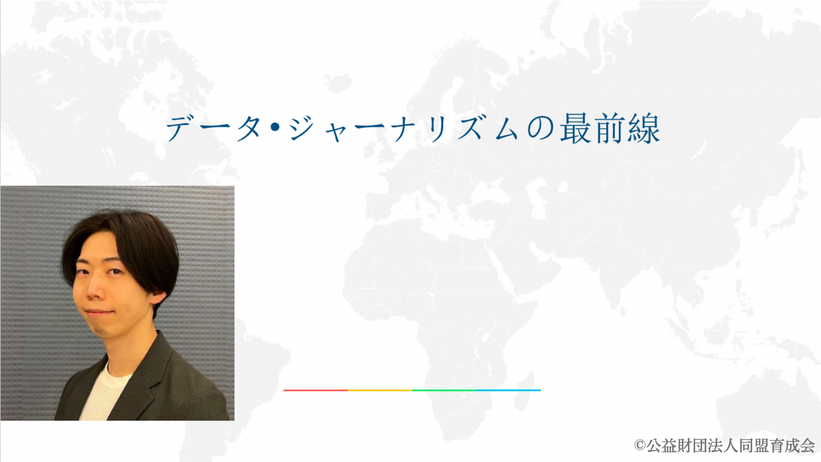
続いて、DataGraphicsInc.代表の荻原和樹氏が「データ・ジャーナリズムの最前線」の演題で講演しました。東洋経済新報社勤務時に「新型コロナウイルス感染症の国内感染状況」のビジュアル化でグッドデザイン賞を受けたこともある荻原氏は「可視化」「変化の推移の一覧性」などデータ報道の強みを掲げた後、スマートフォンやタブレットの普及により、紙やテレビにないニュース体験ができるようになったと話しました。具体的にはタップ、スクロール、画面の拡大・縮小といったユーザーの操作でコンテンツに変化が生じるインタラクションがポイントだとしています。また、データ・ジャーナリズムの手法の一つで、情報やデータを視覚的に表現する「インフォグラフィック」の制作過程を、事例を挙げて説明。最近は画面のスクロールとストーリーテリングを組み合わせた造語「スクローリーテリング」が注目を集めていると明らかにし、テキストとグラフィック表現が連動することで情報を提供する事例が増えていることを示しました。
講演終了後、奨学生からは「格差が広がる中で、ジャーナリズムはどの層に向けたものになるべきか」「見せ方を丁寧に吟味したデータと恣意的に構成されたデータをどうやって見分けたら良いか」などたくさんの質問が寄せられました。





